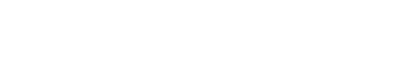サントリーロジスティクス 髙橋範州社長「知見活かし取引増へ」

今年4月にサントリーロジスティクスの社長に就任した髙橋範州氏。大手食品メーカーを経て、2004年にサントリーに入社した。
食品業界で培った経験を活かし、入社後は静岡支店の営業スタッフとして営業企画に携わり、営業側の取りまとめや本社との連携・調整を行った。
その後にビール事業部に約7年、14年にサプライチェーン本部へ。「製品ができてからのマーケティング活動を中心としたこれまでの仕事に加えて、製品が出来上がるまでのバリューチェーンを経験でき、顧客ニーズを考えるうえでの視点拡大を実践することができた。直近では、コロナ禍の時は巣ごもり需要が急拡大し、缶(包材)の調達に奔走したことが印象的だった」と説明する。
グループをあげて持続可能な開発目標(SDGs)に取り組んでいるが、同社では23年、サントリーグループの工場にある食堂や従業員の各家庭から排出された廃食油を回収する「サンロジ油田スポット」を設置し、バイオディーゼル燃料として活用する取り組みを開始した。「現在は、さまざまなことにトライして、その中から最適解を見つけるというステージ」と、自社のSDGsの取り組みを評する同社長。

試行錯誤はSDGsのみならず、物流拠点やセンターへの投資も含む。分散していた倉庫機能を統合・集約した沖縄豊見城配送センターや、浦和美園配送センターではAGF(無人搬送フォークリフト)を導入するなど自動化を推進、今年4月には長津田配送センターに自動搬送ラックを導入した。また協力会社に呼びかけ、動態管理システムを導入するなど自動化やDX化を進めている。
こうした自動化・省人化の大型投資に対し、同社長は「取り扱う貨物のポートフォリオや世の中のインフラが変わってしまい、あるいは違った技術が開発されると、引き返せなくなる可能性がある」との危機感も指摘しており、「導入を検討する際には、下地となるデータを収集することが、この先、数年は特に重要だと考える。また、我々の主貨物または業務に適したアレンジ・工夫が必要」という。
現在、同社の協力会社は300社ほど。この協力会社や、今後取引する企業に期待することを3つあげる。「法令順守、スピード感、そして、長期的な事業ビジョンが合致するか」。
第一にあげるのは「法令順守のなかには労災ゼロを含めた安心安全」、第二に「情報伝達の速さであり、スピード感をもったやり取りができるかどうか」。
第三の「長期的なビジョンが合致するか」の点は、この先5年・10年と同じ方向性でやり取りができるビジョンや土壌があることを求めている。一方で「我々も協力会社から、一緒に仕事をしたいと思える会社にしていく必要がある」と気を引き締める。
今後の展望について、「人材面では、自分の仕事や持ち場に執着と責任を持ち、工夫できる人材やコミュニケーションが多い組織にしたい」という。さらには「そこで得た知見を活用し、例えばサントリー製品の流通加工で培った知見を他社へ活用するなどして、さまざまな業界や企業との取引を増やしていきたい。DX・自動化についてもそれぞれの顧客ニーズの将来予測を十分に行い、取引先、自社、最終ユーザーにとって、有用性が高い選択を検討していきたい」との思いを語る。
◎関連リンク→ サントリーロジスティクス株式会社