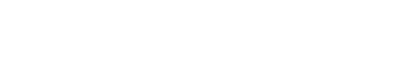日清食品 深井常務 サプライチェーンを一体化「全体で効率化に向け歩み寄りを」

カップヌードルやどん兵衛、カレーメシなど即席食品を製造・販売する日清食品(安藤徳隆社長、東京都新宿区)。同社は荷主企業として、実運送事業者とのコミュニケーションを図り、物流2024年問題への注目が集まる前から共同輸送などに取り組み、2023年にはJA全農、昨年7月には伊藤園とラウンド輸送を開始した。
取り組みの中心を担っているのが、事業統括本部とWell―Being推進部の部長を務める常務の深井雅裕氏。深井常務は「物流やサプライチェーンの改革のゴールは、Well―Beingの実現につながる。社会課題の解決が物流の2024年題の解決だと位置付けている」と話す。
「サプライチェーンは物流という一部だけでなく、生産や販売まで見ていかないと最適化は難しい」とし、同社は営業とサプライチェーンを一体化して事業統括本部とする体制作りを行った。
カップラーメンの繁忙期である12月は、夏の2倍の需要があり季節波動が大きい。即席麵は一つひとつが軽いので、重量積載率の面では最大化が難しいという特性がある。
「こうした波動をいかに平準化していくか。消費特性や製品特性が異なる業種を超えた組み合わせは物流の効率化に寄与すると思う」と同常務。JA全農や伊藤園との提携も、こうした問題意識を持った双方が話し合った結果だ。

「当事者が集まって話す場が必要。ここ数年で『なにかやらないと』という機運が高まっている。この流れを止めたくない」とし、「社会課題をみんなで解決していくということをやっていけるのではないか」と期待する。
「物流については部分的な『切った貼った』ではなく、サプライチェーン全体をみていかないといけない。改革を進めていくなかで、物流の各プロセスにおいて凸凹が出てくるが、そこは部分最適ではなく、全てのコストの負担者は消費者なので、サプライチェーン全体で効率化に向けて、全ての関係者が歩み寄らないといけない」
「付帯作業は本来であればどの立場がやってもいい仕事だが、もちろん『無料』ではないことを示し、どの立場のプレイヤーが付帯作業をやっていけば、持続可能な物流となるか全体を見る必要がある」と話す。

そのためには「サプライチェーン全体の業務を可視化し、全体の仕事を一度ばらし、データ共有すること」と同常務。さらに、競合他社や荷主企業同士とも物流に関しては仲間意識が持てるという。
「サプライチェーンはインフラだ。全体が変わっていかないといけない。どうやって活用していくかは、全体で情報交換をする必要がある」と力説する。
◎関連リンク→ 日清食品グループ