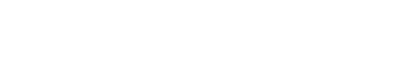ENEOSが取り組むドライバー確保と安全対策

日本全国に石油燃料を供給する元売り大手のENEOS。その物流を担うのが、鉄道と船、そしてタンクローリーだ。同社では、タンクローリー輸送を協力会社に委ねているが、輸送が全国に及ぶため、各地に多くの協力会社を抱えている。今回、その協力会社の窓口として、燃料油陸上配送の契約・管理を担当する販売企画部配送企画グループチーフスタッフの企画チームリーダーである根本和汰氏に、同社の安全対策や物流の2024年問題、ドライバー不足が深刻化する実運送会社の課題について話を聞いた。

燃料油陸上配送は冬に繫忙期を迎えるが、タンクローリー輸送は24時間・365日稼働している。製油所で燃料油を積んだタンクローリーが早朝に出発、そこからSSや工場に配送する。通常、1日に2、3回の配送を行い、夕方に仕事を終えるのが基本だという。
全国各地に製油所や油槽所を配置しているため、拠点を軸とした地場輸送がメインとなる。需要の多い地域では、2人体制で朝と夕方のシフトを組んでいるケースもある。
根本氏が所属する部署では、石油製品の安定供給に必要なタンクローリーの数を計算し、全国の協力会社と必要な台数を契約している。
専属契約している「ENEOS」マーク入りのタンクローリー(マーク車)には、独自の運行管理システムを導入しており、タンクローリーの配送状況をリアルタイムで確認している。

また同氏によると、「ENEOSの仕事をする専属契約を結んでいないタンクローリーには、運行管理システムの搭載をお願いしており、今どこに配送しているかをほぼ100%把握できる環境を構築している」という。
ドライブレコーダーやブレーキシステムといった安全対策に係る装置については、設備投資が必要であるため、対応は協力会社に委ねられるというが、「契約している大半の運送会社は、積極的に装置を導入している」という。
同社では必要台数を確保するため、多数の協力会社を有しているが、今年4月から義務となる実運送管理簿台帳や多重下請け構造の是正には、「再委託先はいわゆる二次請けが多く、当社としても課題ととらえている」とし、「直接契約に切り替えると、契約窓口が増え大きな負担になるが、いまのままでいいとも思っていない」と改善を示唆する。
さらに安全な輸送を行うには、協力会社の確保や、それに伴う運賃改定、ドライバー不足の解消など課題があることも認識しているという同氏は、燃料油という特殊製品の輸送にそれ特有の課題も感じている。
石油燃料を運ぶ運送事業者は荷量の少ない夏にドライバーの数をそろえ、冬の繫忙期に備えることが多く、これまでは荷量の少ない夏に、ほかの仕事を獲得することは、各協力会社の努力に任せていたという。
しかし、運送会社の自助努力だけでは限界もあり、「平準化はとても難しいが、自社の課題としても取り組まないといけない問題」と同氏は指摘する。
ただ、同社ではこうした課題をただ手をこまねいていたわけではない。2018年3月から、段階的に協力会社の運賃の値上げを行ってきた。ドライバーの賃金アップや労働時間の改善、そしてローリー車の確保を目指すためだ。
働き方関連改革法案が閣議決定されると、残業時間の規制(2024年問題)に対応するため、配送に必要なローリーの実働時間を9.5時間で収めるよう取り組んだ。
2018年以降は物流コスト上昇を配送の効率化で対応してきたが、今後は石油製品の卸価格に反映することで対応していくという。
「物流効率化を進めるなかでともすれば現場の声は蔑ろにされやすい。丁寧なヒアリングを重ね、安定供給に向けてドライバーを雇い続けられるよう運賃の改定などに取り組んだ」という同社にあって、「まずは今までの配送が継続できるようにした」と同氏はいう。
現状さらに物価や人件費上昇もあり、運賃の定期的な見直しについて、「各社の稼働台数や契約台数の状況などを参考に、各協力会社と話をしている状況」と説明する。
加えて、「ドライバー確保は大きな課題」だとし、「賃金を全産業と比較して見劣りしないレベルに引き上げられるよう取り組んでいきたいところ」としつつ、「賃金だけではなく、土日の出勤や、早朝・夜の勤務を避けるなど、どう対応していくかを考えていかねばならない」と課題をあげる同氏は、「ただ運転すればいいだけではなく、危険物を扱う難しさ、プロフェッショナルさに注目をして、興味をもってもらう取り組みも行っている」とし、昨年はCMと並び、YouTube動画を作成してPRしたという。
「ドライバー確保は協力会社各社で取り組んでいることだが、荷主としてPRできることは今後も行っていきたい」とし、荷主として協力会社のドライバー確保に貢献していく考えだ。
◎関連リンク→ ENEOSホールディングス株式会社