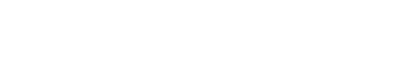「梱包が物流を変える」 東日本梱包工業組合 三浦康英理事長

梱包業界には、全国をまとめる日本梱包工業組合連合会(谷川隆二会長、東京都大田区)のもと、東日本と西日本に梱包工業組合がある。西日本は谷川会長が兼任。東日本梱包工業組合の理事長を務めるのは、サンリツの三浦康英会長だ。今回、三浦理事長に梱包業界の現状と魅力について話を聞いた。
梱包業界が抱える大きな課題として、「人材不足と高齢化がある。梱包の技術を受け継ぐには、職人的な現場のきつさがある。初めから匠の技を引き継ごうとして強い意志を持って入ってくる人もいれば、ただ物流の会社に入っただけという人もいる。そういう人は、梱包の現場で長く続くかという問題があり、なかなか難しい」という。
また、梱包が物流のポジションの一つでありながら、大きく取り上げられにくいということもある。それに対し三浦理事長は「梱包業の歴史をたどると、60~70年前の梱包というのは、輸送サービスの一つでしかなかった。運ぶために荷造りをする作業であって、そのための対価は支払われなかった。たとえば、一番最初は縄で縛るとか、商品を運びやすいようにするためだけだった。それが〝運ぶ商品を守るため〟に切り替わった時から、専門会社ができ、この業界ができた。梱包もして運送もすると。その仕事のなかで、中身の製品をどうしたら守れるかという技術が高まった」という。

そして、「米軍の規格から始まった日本のJIS規格にこの業界が取り組んで、何度も改善して環境にあった規格に変えていき、今の梱包業界になった。この規格をつくる工程で、教科書的なものもできた。それによって、誰にでもできるよう平準化がなされたために、梱包の技術に対して、荷主さんやメーカーさんが当たり前と思うようになってしまった。商品を無事に届けてくれることは、実はちゃんとした技術の一つなのに、技術として認められていない現状が出来上がってしまった。だから今後はまず、しっかりと技術として認めてもらうことが必要。それによって、梱包というこの仕事に魅力を感じて、業界に入ってきてくれる人材もいるのではないか」と話す。
さらに「梱包技術、梱包の仕事をブランド化するために業界で青年部会を設立した。業界の若手経営者をはじめ、若い人たちの感覚で、どうやってPRしていくか、という活動を始めている」と続ける。
自身も梱包管理士の資格を有する三浦社長は、梱包の仕事の魅力について、「まずは匠の技。これは誰にでもできることではない。JIS規格があり、教科書もあるので、頭のなかで、理論上では誰にでもできるはずだが、実際には現場で、体で覚えないとできない。そこに対する魅力をすごく感じている。つまり、梱包技術は職人芸であり、同じように作っていても、その商品にあわせた固定技法とか、緩衝設計とかがさまざまで、各梱包会社でも違ってくる。毎回、自分の技量を試されているような感じで、一品一様のものがほとんど。きちんと梱包し、無事先方に到着した時点でようやく一つの仕事が完成する。今の若い方たちに、一つの仕事をやり終えるやりがいを感じてもらえたら、面白さも分かってもらえるのかな」と語る。
梱包業界では技能実習生を受け入れ、早くから外国人雇用を進めてきた。「真面目な方が多い。今回、梱包が特定技能として認められた。いずれ外国人の梱包管理士も生まれるかもしれない」。
「梱包方法によって物流も変えていくことができる。たとえば、製品の突起物をひとつ減らすだけでも輸送は変わる。こういう梱包をするからこういうモノづくりをしてくださいと言えるようになったら、物流全体が変わっていく。それが大きなテーマだろうと思っている」との思いを語る。
◎関連リンク→ 東日本梱包工業組合