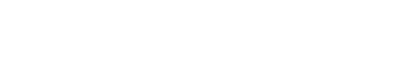TGL 特別教育の効果は? 定期講習に悩む社長も
63回閲覧
-700x468-2.png)
Image: weekly-net.co.jp
テールゲートリフター(TGL)を使う荷役作業者に対し、特別教育の実施が義務化され1年半がたつ。荷役作業時の墜落、転落が後を絶たないことを受けて2023年に労働安全衛生規則が改正されたもので、TGLを使うドライバーや庫内作業員は、学科4時間と実技2時間の合計6時間の受講が必須になっている。決して短くない時間の教育を受けることで、荷役時の事故を防ぐ意識が高まることが期待されているが、実際に労災事故は減ったのか。事業者に聞いた。
◇
広島県内で日用雑貨を運ぶA社。実は5年ほど前に出入りする物流センター内で死亡事故を起こしたという。社長によると荷台とバースの間にドライバーが挟まれるという痛ましい事故だったそうで「以来、現場での声掛けや指差し確認を徹底するようになった」と話す。
同社は保有する車の半数にTGLを装備するが、「2年前に法改正があった直後に安全担当者がインストラクターの養成講座を受け、指導用に自社で資料も作った」という。先の声掛けや指差し確認の効果もあってか、荷役中の事故は目に見えて減ったという。
-700x468.png)
また、食品を中心に運ぶ中堅のB社の社長は、「センターを含めて対象者が多く、入れ替わりもあるので教育体制を作るのに苦労した」と振り返る。半年ほどかけて準備し、対象者全員が講習を受け終わって、特別教育が義務化された昨年2月を迎えたという。
事故件数は「もともと年に数回、軽微なものがあるが、いまのところ特別教育以前と変化はない」そうだ。しかし、「せっかく講習を受けても、日々の業務のなかで慣れて、いい加減になることが怖い。定期的に復習する機会を作るべきか悩んでいる」と話している。