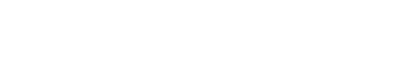第294回:令和時代の運送業経営 残業時間削減編(91)

【歩合設計編】91
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号から「歩合設計編」として時間外上限規制(2024年問題)への給与設計面での対応について解説してまいります。(その1)
1.24年問題と給与制度
ドライバー不足と貨物運送量の減少が社会問題化し、物流2法(貨物自動車運送事業法、物流総合効率化法)などにより多重下請け構造の是正、契約の書面化、運賃の下限設定などについて法制化されてきており、運送業界は24年問題を契機に歴史的転換点を迎えています。
さて、24年問題は運送業の給与制度設計に大きな影響を与えています。これまで「1運行〇〇円」「1コース〇〇円」「月の売り上げの〇%」といった考え方で指示・配車される運行に対し、ドライバーもそれを当たり前として実施してきたというのが実態でした。「時間意識」が希薄であったなかで、この問題に取り組まなくてはならなくなりました。
なお、現状では物流の担い手である運送業を守っていくという考え方があるため、法改正後の規制に対応していない会社を摘発するという動きにはなっていませんが、現実にはトラックによる痛ましい事故のニュースが報道されており、徐々に「摘発モード」になっていくことが想定されます。Gメン制度の創設や運賃上昇を後押しする施策を推進されるなかで、時間外規制に対し真摯に取り組んでいる会社とそうでない会社を分けていくという考え方は理解できます。
さて、給与制度は「時間外労働時間数」が重要な要素です。
皆さまの会社では労働時間数を正確に把握できているでしょうか? この紙面でも何度も解説していますが、ドライバーの労働時間数はデジタコ、点呼システム、ドライブレコーダーを連動させ、勤怠管理システムを活用し把握するのが望ましいです。今後の法改正でも時間把握を目的としてデジタコ利用が推奨されていく見込みですが、やはり分単位の休憩時間の把握や動態管理の必要性などによりデジタコ活用は必須です。変形や日跨ぎ運行など複雑な運行形態にも対応する勤怠管理システムも進化しています。
正確な労働時間の把握は事業者の義務であり、24年問題は給与制度を改革していく大きな契機となりました。
2.月給制、日給制、時給制
多重下請け構造は中期的には是正されていく見込みですが、中小運送業者の実態としては長時間労働を余儀なくされる会社がまだあります。定期配送など固定的運行であれば時間管理も容易であるため月給制・日給制・時給制といった労働基準法の原則通りの設計をしても大きな問題になりませんが、変動的な運行の場合は問題になる場合があります。