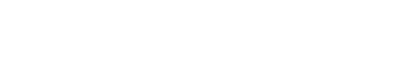金融政策は今の物価上昇に対処できるか?—金利引上げの是非を考える
48回閲覧

先日の日銀政策決定会合(10月29〜30日)で、追加利上げは見送られました。この判断に「生活苦の原因となる物価高をそのままにしている」「低い金利が円安を促進し、さらなる物価上昇を招いている」「経済環境が変化したのに政策が追いついていない」などの批判の声があがっています。
これらの意見を要約すると、「現在の物価高に対して金利上昇で対応すべき」「円安抑制のために金利を上げるべき」「低金利が企業の生産性向上を妨げている」という三つの主張になるでしょう。あなたも日々の買い物で物価上昇を実感していませんか?
データを見てみましょう。確かに2025年9月時点で、生鮮食品を除いた消費者物価指数は3.0%、エネルギーを除いても3.1%上昇しています。しかし、食品とエネルギーを両方除いた場合は1.3%にとどまっています。「食品もエネルギーも私たちの生活には欠かせないものなのに、なぜ除外するのか」という疑問が湧くかもしれません。
この疑問は理解できますが、重要なのは「金融政策で対応できる物価上昇とは何か」という点です。天候に左右される生鮮食品や国際情勢に影響される原油価格の変動に、金利操作で対応することは適切でしょうか?例えばコメ価格は今年、前年の2倍になりましたが、この上昇率は既に下降傾向にあります。
これらの一時的な価格変動も含めて平均物価上昇率を2%に抑えようとすれば、他の商品・サービスの価格を引き下げる必要が生じます。そうなると、ようやく抜け出しつつあるデフレに逆戻りするリスクも考えられるのではないでしょうか。金融政策の役割と限界について、私たち一人ひとりが考える時期に来ているのかもしれません。
業務効率化は運ソウルで解決!:https://doraever.jp/lp_unsoul
※本記事およびサムネイル画像は一部AIによって生成・編集されています。内容については十分確認しておりますが、情報の正確性・最新性については保証いたしかねますので、最終的な判断はご自身の責任にてお願いいたします。