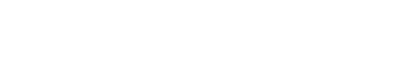東日本梱包管理士会 安達正明会長 やり方工夫し進化「梱包は面白い仕事」

東日本梱包管理士会(安達正明会長)が今年、創立50周年を迎える。昨年8月に就任した安達会長に、自身のこれまでの略歴と梱包業界について話を聞いた。
梱包管理士は、大型商品や重量物などを海外に出荷する際、輸送時の衝撃などを理解し、荷物を保護するため木枠で梱包するなど、いかに必要最小限の材料で耐久性のある梱包をするかが求められる資格だ。日本梱包工業組合連合会が認定する。
安達会長は、安達包運倉庫(愛知県弥富市)の4代目社長。昭和13年創業、37年設立の同社は、梱包、倉庫、運輸の3本柱で事業を行っている。「私は初め、総務の仕事から入り、倉庫、運送と経験して最後に梱包の仕事に携わった。梱包業から始めた会社だが、当時の梱包業は決して良い業界ではなく、運送や倉庫は好調だった。社長である父親が倉庫を、父の弟である叔父が梱包を担当していた」。輸出業が盛んになり、同時に梱包業が一気に伸び始めた時、会社拡大のため名古屋市から弥富市に移転し、主業を梱包へと大きく舵を切った。「自分も叔父の後を追って梱包を担当。まずは資格が必要と資格試験を受け、梱包管理士の第17期生になった」と振り返る。

「資格を取るための勉強を始めた当時、梱包の知識は何もなかったが、だからこそ、固定観念などもなく、ひたすら素直に学習して覚えるだけで、入り込みやすかった」と話す。「15、16年前は日本製のモノが世界にどんどん出て行き、世界のあちこちに設備投資した時代。そのころは輸出が活発な時代だった。しかしコロナ前には設備投資もほぼ終息し、日本企業が海外に出ても、現地で調達するようになり、日本からの輸出量が減った」と現状を分析する。
また「梱包管理士は、梱包する商品だけを見るのではなく、輸送全般を見る必要がある。資格を取った以上は梱包のプロという感覚でやらねばならない」とし、「梱包業では営業担当者も、ぜひ梱包管理士の資格を取っていただきたい。梱包管理士は、現場を見ながら営業し、成果書まで作る。現場の状況が分からなければ営業はできないので、営業のツールとしても資格は非常に有効。直接仕事を取ってくる、仕事に関わって仕事を回していく人になること。会社の経営者もそれを期待して資格を取らせているはず」と語る。さらに「仲間づくりも大きなポイント。組合や管理士会に入ることで、同期の仲間もでき、助け合い、情報を共有し合う大きな力になる。価格の設定や交渉に関しても、全国的な相場の情報など相談できる点もメリットとなっている」
。

梱包分野では、技能実習制度創設時から対象分野として外国人の受け入れが始まり、現在では特定技能の対象分野にも追加された。「個人の能力差はあるが貴重な戦力として必要。いつか外国人の梱包管理士が誕生する可能性もある。頑張れば資格取得もできると周知し、取得者が出てくれれば幅が広がるのではないか」とも。
安達会長は「梱包は人それぞれのやり方があって面白い。常にもっと良い方法はないか考え、釘の本数や筋交いの入れ方を工夫する。基本はあるが、さらに安くて良い方法を探り、自身もアップデートしていく。ほかの人の梱包を見て刺激を受ける。資格取得によって基本を持ち、仕事に興味を持つ人はぐんぐん伸びていく。まだ資格を取っていない人はぜひチャレンジし、梱包管理士会の仲間になっていただきたい」と語る。
◎関連リンク→ 東日本梱包管理士会