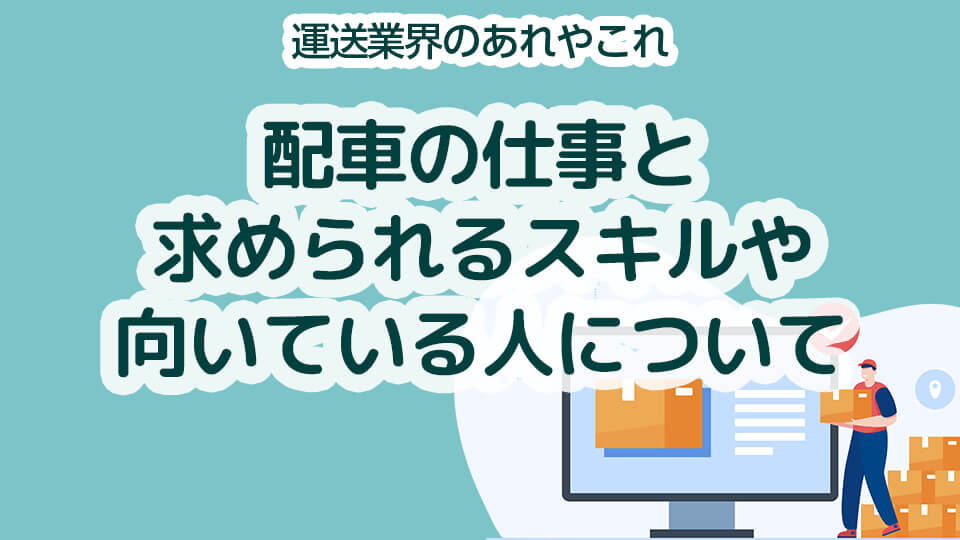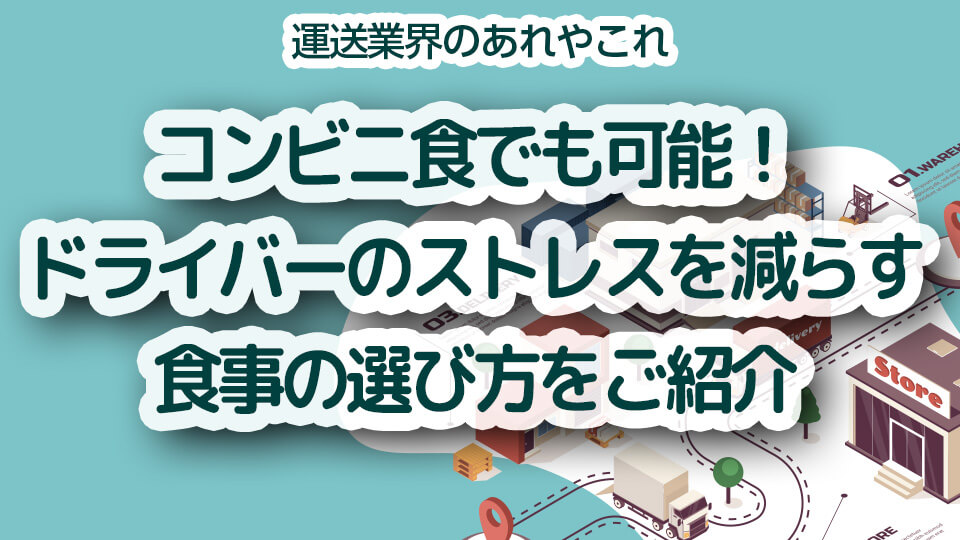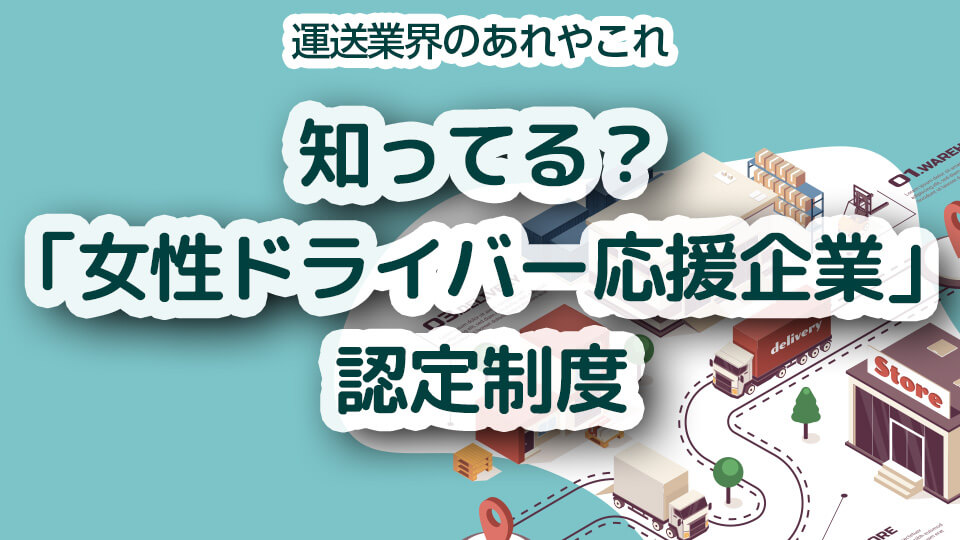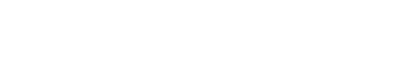食事で眠気とストレスは防止できる!ドライバーのための食事術
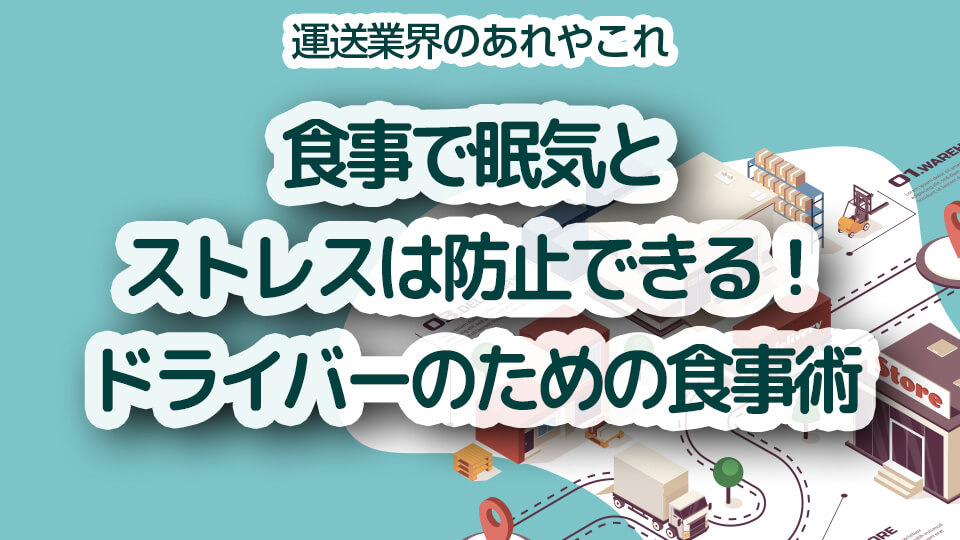
長時間運転を続けなければいけないトラックドライバーにとって、ストレスと眠気は天敵とも言える存在です。
仮にストレスが溜まっている状態で運転を続けると、事故のもとになりかねません。
また、眠気を感じている状態で運転をすれば、悪い影響は避けられないでしょう。
ストレスや眠気を防止する方法はいくつかありますが、今回は食事にフォーカスしながらレクチャーしていきます。
そもそも眠気はなぜ起こる?
基本的に、運転中に眠気を感じるのは、睡眠時間が足りていないからです。
人間にはそれぞれ必要な睡眠時間があり、それに満たなければ体は悲鳴をあげます。
眠気は、いわば体からのSOS反応と言えるでしょう。
トラックドライバーに限らず、しっかりとした睡眠時間を取るのはとても大切なことです。
とはいえ、中には十分に睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中に眠気を感じるという方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、血糖値スパイクが起きている可能性が否めません。
人間が糖分を摂ると、それを血の中に流して処理しようとします。
血糖値は、糖分が血の中にどれくらいあるかを示す指標です。
たとえば、甘いものを食べ過ぎたり、ご飯やパンなどといった糖分だらけのものを食べたりすれば、血糖値は急激に上昇します。
血糖値が急激に上昇すると、体はインスリンを放出して糖分を急速に処理しようとします。
とはいえ、インスリンが膨大に放出されれば、体に大きく負担がかからざるを得ません。
このように、血糖値が急激に上昇した後に、急下降する現象を血糖値スパイクと呼びます。
日中に眠気を覚えてしまう原因は、おおむね血糖値スパイクにあると言えるでしょう。
日中の眠気を抑えるための食事
先ほどは、日中の眠気の原因が血糖値スパイクにあるという説明をしました。
では、こうした血糖値スパイクを防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。
最初に述べておきたいのは、血糖値スパイクの原因が糖分ならば、糖分を摂らなければ良いなどと短絡的な考え方をしてはいけません。
糖分は、人間にとってエネルギーになる大事な栄養素です。
摂りすぎてもダメですが、摂らなすぎてもいけません。
仮に、糖分を摂らないまま運転すると、かえって集中力がなくなってしまうでしょう。
では、糖分を摂りつつ血糖値スパイクを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。
ここで注目したいのが、食べ物のGI値という指標です。
GI値は、簡単に言えば糖分の吸収速度を示す指標です。
GI値が高ければ高いほど血糖値は上がりやすく、低ければ低いほど血糖値は上がりにくくなります。
たとえば、GI値が高いものの代表として白米が挙げられますが、GI値が88です。
白米はおいしく、エネルギー源としては優秀な食べ物ですが、食べ過ぎると血糖値が上がってしまうので注意しましょう。
逆に、精製されていないお米である玄米は、GI値が55と低めに設定されています。
眠気を防ぎたいけれど、お米は食べたいという人にとって玄米は極めて優秀な食材と言えるでしょう。
また、玄米はストレス解消の観点から見ても優れた食材です。
玄米は、精製されていない分、白米と比べてたっぷりと栄養が含まれています。
その中の一つにGABAという成分があるのですが、これはストレス解消を促進する栄養素です。
それに加えて、玄米は白米に比べて硬いので、よく噛んで食べなければ消化しきれません。
この噛む動作がストレス解消を促してくれるので、ドライバーにとっては必須食品とも言えるでしょう。
コーヒーやお茶はタイミングを重視しながら飲むべし
トラックドライバーにとって、カフェインが含まれているコーヒーやエナジードリンクは必需品と言えるでしょう。
眠気を抑えるという意味では悪い選択ではないのですが、飲み過ぎは禁物です。
カフェインは、眠気を引き起こす脳内物質を抑えるため、夜に飲んでしまうと眠れなくなってしまいます。
この結果、睡眠時間が短くなってしまい、眠気を抑えるためにコーヒーやエナジードリングをがぶ飲みするようになってしまったら元も子もありません。
コーヒーは夕方以降は避けたほうが良いでしょう。
また、ストレス解消の観点から言えば、コーヒーよりもお茶のほうが効果は高いです。
お茶にはテアニンという栄養があり、これはストレス解消に効果てきめんです。
また、テアニンは睡眠の質を良くしてくれるという効果もあります。
テアニンは、カフェインの効果をマイルドにする効果もあるので、コーヒーやエナジードリンクを飲んだ時に心拍数が上がりやすいという方にはおすすめです。
まとめ
今回は、眠気やストレスを防止するための食事術について解説してきました。
最後に一つ付け加えておきたいのは、3食を規則正しく食べることです。
しっかりとした食事をしなければ健康は成り立ちません。
トラックドライバーは体が資本なので、健康に気を使いながら食事をし、いつまでも仕事ができるような工夫をするようにしましょう。