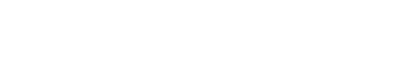鉄道分断で露呈した物流網の脆弱性―JR貨物の危機対応戦略
43回閲覧

10月6日から16日早朝まで、自然災害による土砂流入で東海道本線の由比・興津区間が機能停止した。この出来事は旅客輸送においては代替手段で対応できたものの、国内物流に深刻な影響をもたらした。なぜなら、この区間は全国の貨物列車運行数の約18%にあたる90本が毎日通過する重要な物流動脈だからだ。
皆さんの生活を支える物流はどのように維持されたのだろうか。JR貨物は緊急対応として複数の戦略を展開した。まず、東京・静岡・西浜松間でトラックによるコンテナ輸送を実施。西浜松からは列車を再接続させ、西日本への輸送を確保した。さらに迂回路の活用も不可欠だった。上越線や日本海ルート、中央線経由など普段は使わない経路で貨物を運び、最大で日量約2000個の輸送能力を維持したのだ。
しかし、こうした努力にもかかわらず、JR貨物は「相当なダメージ」を被ったと認めている。荷主への謝罪と代替輸送の提案を行ったものの、「正直に言って対処しきれない部分があった」と吐露。一部の顧客は独自にトラック輸送へ切り替えざるを得なかったという。この事例から見えてくるのは、私たちの暮らしを支える物流ネットワークの重要性と、同時にその脆弱性だ。あなたが普段何気なく手にする商品の多くが、実はこうした鉄道輸送に支えられていることを、改めて考えてみてはいかがだろうか。
車輛に関連する問題は運ソウルで解決!:https://doraever.jp/lp_unsoul
※本記事およびサムネイル画像は一部AIによって生成・編集されています。内容については十分確認しておりますが、情報の正確性・最新性については保証いたしかねますので、最終的な判断はご自身の責任にてお願いいたします。