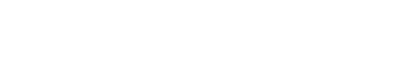都内火葬費用の急上昇問題―行政介入へ向けた動きと民間業者の実情
54回閲覧

首都圏における火葬費用の高額化が社会問題となっています。この事態を受け、東京都の小池知事は2023年9月30日の定例議会で「民間施設への適切な指導実施に向け区と協力し、必要な法整備を国へ要請する」と発言しました。
全国的には公営施設が主流ですが、23区内では9施設中7カ所が民間運営で、そのうち6カ所を特定企業が管理しています。この企業の運営する施設では火葬料金が9万円からとなり、公営の4〜6万円と比べて大きな開きがあります。
「外資系資本が関与していることと料金上昇は無関係」と当該企業の親会社は説明します。値上げの背景には「燃料高騰や人件費上昇、設備維持費の増加があり、税金による補助がない民間事業としては適正価格」と主張しています。
あなたは葬儀を準備する際、このような料金差をどう考えますか?実際に低所得者向け葬儀支援を行う団体関係者は「多くの方が高額でも民間施設を利用せざるを得ない状況」と指摘します。行政の介入で状況改善が期待される一方、施設側は「事業継続のための必要な価格設定」と反論しています。
料金推移を見ると、2021年に約10年ぶりの値上げが行われ、2022年には変動制が導入され、2024年からは9万円の固定料金となりました。資本構成の変化と値上げ時期が重なったことで批判が集中していますが、企業側は「収益は将来の設備メンテナンスのための内部留保」と説明しています。
公共インフラの料金設定において、適正価格とは何か。利用者の負担と事業継続性のバランスをどう取るべきか。この問題は私たち全員に関わる重要な課題ではないでしょうか。
業務効率化は運ソウルで解決!:https://doraever.jp/lp_unsoul
※本記事およびサムネイル画像は一部AIによって生成・編集されています。内容については十分確認しておりますが、情報の正確性・最新性については保証いたしかねますので、最終的な判断はご自身の責任にてお願いいたします。