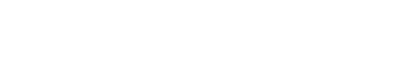組織のサイバー回復力強化 – 医療現場から学ぶ危機対応の新視点
67回閲覧

デジタル製品を取り巻く脅威が進化する現代、組織の危機対応能力の抜本的な見直しが求められています。「ITmedia Security week 2025 春」で注目を集めたのは、ソフトウェア協会の萩原健太氏による講演でした。あなたの組織は予期せぬサイバー攻撃に耐える準備ができていますか?
世界的な潮流として、欧州ではデジタル製品の安全性確保と消費者保護を目的とした包括的な規制が整備されています。この枠組みでは、開発過程のセキュリティ確保、脆弱性への対処責任、情報開示の徹底、そして適合性の評価という四つの柱が重視されているのです。
一方、我が国も米国、豪州、インドと連携し、政府調達ソフトウェアに関する国際的な安全基準の策定に参画しています。この取り組みでは、NISTのフレームワークに準拠した安全な開発手法の導入が推奨されています。こうした動きに合わせ、自社製品のセキュリティ品質向上と危機発生時の対応を担う専門チーム「PSIRT」を設置する企業が増加傾向にあります。
「開発プロセスの透明性向上なくして、効果的な危機対応は実現しない」と萩原氏は強調しています。あなたの組織は透明性と危機対応力のバランスをどのように取っていますか?今こそ、サイバー空間における組織の回復力について真剣に考えるべき時なのかもしれません。
業務効率化は運ソウルで解決!:https://doraever.jp/lp_unsoul
※本記事およびサムネイル画像は一部AIによって生成・編集されています。内容については十分確認しておりますが、情報の正確性・最新性については保証いたしかねますので、最終的な判断はご自身の責任にてお願いいたします。