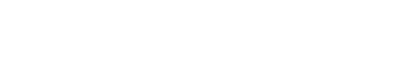庶民の足を生み出した戦略と革新 ~大衆車市場の幕開け~

日本の自動車史において、1966年は一般市民が初めて手が届く乗用車が登場した転換点として専門家の間で広く認識されています。この年、日産とトヨタが発表した小型車が、日本のモータリゼーションを加速させる起爆剤となったのです。
それまでの自動車市場は、会社役員向けやタクシー事業者が顧客の中心でした。一般家庭にとって、車は依然として高嶺の花。富裕層の奥様が買い物に使ったり、成功した商店主が業務と休日兼用で活用したりする程度でした。一般給与所得者にとっては、軽自動車すら気軽に購入できる時代ではありませんでした。
こうした状況を打破しようと、日産の若手技術陣が立案したのが「月給取りでも所有できる車」という発想です。収入増加が実感できるようになった高度経済成長期、人々の自家用車への憧れは日に日に強まっていました。しかし、この画期的な企画は当初、経営トップからの理解を得られませんでした。「予算の限られた人は中古車で十分」という旧来の考えが壁となったのです。
開発チームは諦めず、商用バンという切り口で計画を進め、並行して乗用車も密かに準備するという戦術に出ました。完成した試作車の出来栄えに経営陣も納得し、ついに発売の承認が下りたのです。皆さんは想像できますか?発売前の命名公募には、たった1か月で800万通を超える応募が殺到する熱狂ぶりを。
こうして誕生した新型車は、明るく開放的な室内空間、直線的で新鮮なデザイン、そして手頃な価格が特長でした。当時の中堅管理職なら、分割払いで手が届く金額設定が功を奏し、発表年の年末には月間販売台数が1万台を突破。経営者も「私が間違っていた」と認める大成功を収めたのです。
軽量ボディに新開発の1リッターエンジンを搭載したこの車は、走行性能でも高評価を獲得。あなたも知っているこの国民車は、その後の日本人と自動車の関係を根本から変えることになりました。かつては特権階級のシンボルだった自動車が、一般家庭の必需品へと変わる瞬間だったのです。
車輛に関連する問題は運ソウルで解決!:https://doraever.jp/lp_unsoul